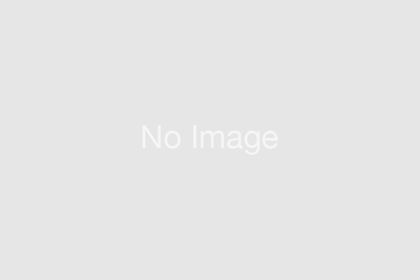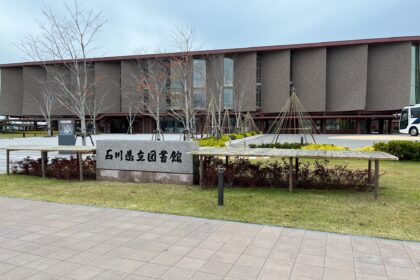令和7年度第2回家庭生活委員会を開催しました
令和7年度第2回家庭生活委員会を開催しました
11月15日(土)13:30より、文教会館202会議室において第2回家庭生活委員会が開催されました。参加者は9名で、地区代表校全校にご参加をいただきました。
第1回委員会後に実施したアンケートでの「スクールカウンセラーの方の講演が聞きたい」との要望を踏まえ、前半はスクールカウンセラーの俵美留子氏に、「お子様の健やかな成長を願って ―高校スクールカウンセラーからの一言―」と題してお話しいただきました。
不登校に関しては、親に相談するときが不登校の初期ではなく、ずっと苦しんできてやっと親に言えた、と考え、少し元気が出るのを待つ勇気が必要であること、スマホに関しては制限から入らず、スマホは生活の必需品だよね、と共感しつつ話を聞くことが大切であること、等をお話しいただきました。また、グレーゾーンについての相談は教員から受けることが多く、板書のノートが取れない、なども本人が取ろうとしていない場合以外に、ノートに書く前に忘れてしまう、先生の指示が分からない、等の原因が考えられ、日頃から配慮の実績を積み重ねることで大学受験でも配慮してもらえる、とのお話もうかがえました。
後半は、事務局の山口文彦氏から北欧の社会と教育」と題して、来年度の北信越大会での講演にもつながる内容でお話をいただきました。
3年に1回行われるPISA調査(国際的な学習到達度調査)において、フィンランドは近年順位を落としていますが、自分の生活に満足しているかを示す幸福度は8年連続世界1位を達成しています。逆に日本はPISA調査の順位は向上し、近年は上位で安定しているものの、幸福度は147か国中55位と、それほど国民が幸せだと思えていない現状が見られます。フィンランドにおける大学と高等職業専門学校は同等で、高校及び職業学校進学率がそれぞれ約50%、高校卒業後にそのまま大学に進学する率も約30%と、若者が自分の適性を見つめ、熟考して進路を選択する現状があるようです。ちなみにフィンランドでは大学院まで授業料は無償で、学校教育は児相ソーシャルワーカーやカウンセラー、医師、作業療法士、警察官などの様々な専門家によって初めて成り立ちます。日本のようなPTAはありませんが、その分、日本の保護者と教員が教育ベクトルをすり合わせ、一貫した教育を確立できればフィンランドの専門家による教育以上の教育的効果を発揮できるのではないか、とのことでした。
参加された皆さんが研修した内容を各地区や学校に還元していただければ幸いです。
なお、家庭生活委員会は、委員の方が出席しやすいように来年度も土曜日開催とする予定です。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA